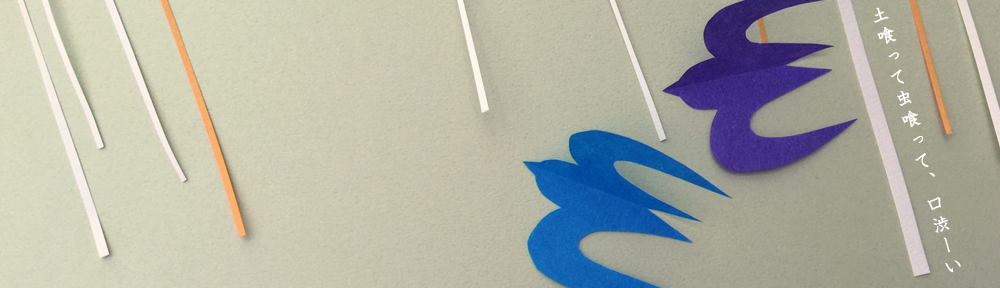2019年6月5日(水)に東京・南青山 折形デザイン研究所 で開催された 旧暦のリズムで日本の行事を再発見する もんきりワークショップ 『旧暦カフェ 第11回「端午」 』のレポートが、さっそく届きました。
菖蒲と蓬で軒を葺く
新暦の5月5日にはスーパーでも売っている菖蒲ですが、旧暦の今はなかなか手に入らない!
今回はYさんのおかげで、こんなに根っこのちゃんとある菖蒲!が入手できました。
何よりの喜び。平安時代に「菖蒲の根合わせ」といって美しく長い根っこを競い合う催しがあったこと、これだったのですね。

でもなぜだろう?根っこにこそ香りと薬効の素があったということかもしれませんね。
つい、地上ばかりに目がいってしまうことを省みなければね。
根を刻んでお酒に漬けて、菖蒲酒も試みました。
強い香りです。
残った根は植えて育ててみよう。
風俗画には藁葺き屋根のわらに差し込んであるのが描かれます。
私達はわら縄に挿してしめ縄風に。
香りの結界です。風にそよぐさまは蒸し暑い中に涼を呼びます。
蓬の茎の紫と菖蒲の根元の桃色が緑に映え、この季節の色だなあと。


粽を作る
初夏の野山を徘徊するうち、これなら使えそうと思う葉っぱを採集。
笹だけではなくいろんな葉っぱを煮てみました。本来は「茅萱で煮たので茅巻という」という言葉に「はて?あんな細長い葉で巻けるのか?という疑問が。
ということで、茅萱の葉も煮てみました。(右のイネ科の草)
アシ、サルトリイバラ、カキ、ヤダケのタケノコの皮、カシワ、ホオ、チガヤ。

これがクマザサの若葉。 枝をつけておくのがコツ。 古くなると白い隈ができる。

まずは3枚を取って

紡錘型(これ、魂の形みたいに感じました)にした団子を包む

巻いて、4枚目を重ねてお尻の部分をたたむ(これが結構難しい)

イグサで巻き上げる

七転八倒、なんと個性ある出来栄え。
でもなんだか力がある。

立ててみました。宇宙の図のようだなあ。

問題のチガヤによる粽も試してみる。なんだか水戸納豆みたいけど。
さて?
これは参加者の方が持ち帰って蒸すことに。
結果をぜひおしらせください。

包む楽しさは、つづく
家に帰ってから、残った葉っぱにもち米を詰めて蒸してみることに。
さて、どんな出来栄えに!?

型破りな粽たちでした。
なんだか おままごと(飯事=真々事?)みたいね。
包む楽しさを知りました。
なんでも包みたくなっちゃった。
これを見て「あ、トトロみたい」とおっしゃった参加者の方がいました。
(トトロが種をつつんで持ってくるシーンですね。)
これらを「トトロ巻」と名付けたい。
「人々を実際に野山に誘う」
そこで草木の生気を浴びること。
食べて飾って、纏って、暮らしに取り込むこと。
それが「端午」という行事の本質かもしれませんね。
しもなかなぼ
2019年6月5日に東京・南青山の「折形デザイン研究所」で行われたもんきりワークショップ 『旧暦カフェ 第11回「端午」 』は、おかげさまで無事に終了いたしました。
菖蒲の根合わせ、草花の香りの結界に守られる家、何かを大切に包む楽しさ、包みをほどく嬉しさ、トトロのような愛らしさ。
ご一緒に、梅雨前の旧暦の暮らしのリズムで「端午」の行事を味わい楽しんでくださったご参加の皆さま、そして折形デザイン研究所の皆さまも、ありがとうございました。
次回の旧暦カフェワークショップは、夏休み開催に向けてただいま準備中です!
次はどんなテーマで、どんな方が集まって、一緒にどんな発見ができるのか・・・詳細決まりましたら小社サイトでもお知らせいたしますので、あなたもぜひご一緒に。
*20190607更新